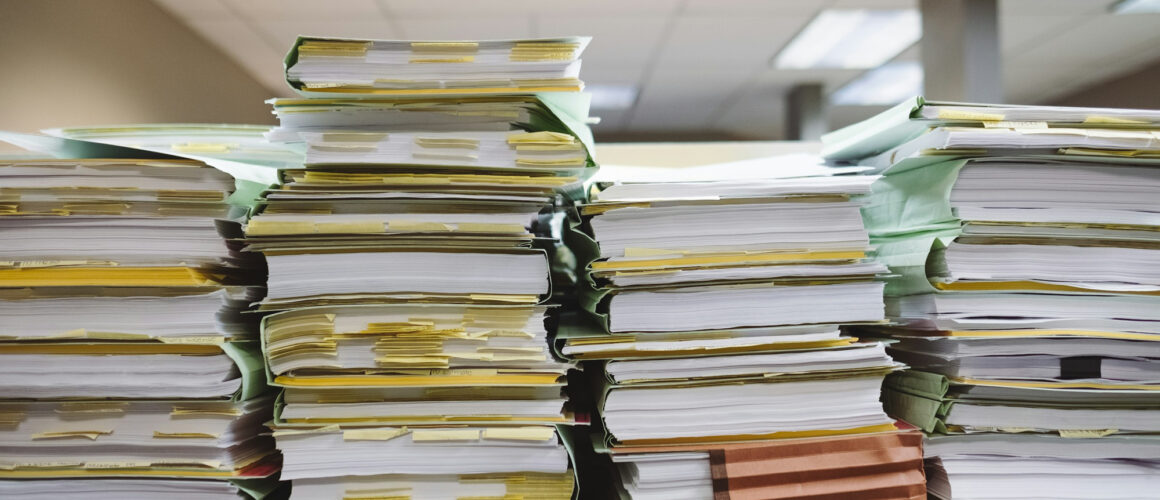ERP知識シリーズ The・MoSCoW 第四部:BPRとMoSCoW【その5】決算日数短縮
前回は「在庫削減=モノの流れ」を題材に、BPRの調味料“さしすせそ”を使って、リアルタイムな仕組みの中でMoSCoWをTo-Be要求へ導く方法を整理しました。
今回はその続編として、おカネの流れをテーマに取り上げます。目的は、前回のBPRによって整えられた“モノの流れ”のリズムを、経理領域のBPRへと波及させ、決算日数短縮といったBPRを通じて経営課題である意思決定の迅速化をどう実現していくかを考えることにあります。
仕事が月末月初に集中する実態
多くの企業では、ERP導入プロジェクトのスケジュールを組む際、経理部門の担当者は「月初は避けてアサインする」ことが了解事項となっています。それほどまでに、月初の経理業務は集中し、部門全体が“締めモード”に入ります。
ERP導入前の企業では、実感として月次決算に早い企業でもおよそ5営業日、長い企業では10日くらいを要しています。
経理が月初に行う主な業務は、仕入・売上・経費伝票の確認、在庫評価や棚卸差異の確定、減価償却や前払費用の計上、売掛・買掛残高の消込、原価差異の算出など、部門をまたぐデータ整合の最終処理です。これらは、購買からの検収データ、営業からの売上確定情報、製造からの在庫・原価データなど、他部門の締め完了を待たなければ経理が仕事を始められない構造です。
バッチ処理からリアルタイム化へ
前回のBPRによって、販売・購買・製造といった“モノの流れ”は、リアルタイムで情報が更新される仕事の仕方へと進化しました。にもかかわらず、経理だけが従来のバッチ処理に留まると、せっかくのリアルタイム化の成果が活かされません。
従来の経理では、“月替わり”をトリガーに集計・評価を行う構造が定着しており、これが経営判断の遅れと現場負荷の主因となってきました。今後は、他部門で確立されたリアルタイムな情報更新のリズムに経理も歩調を合わせ、取引の発生時点でデータを確定させる構造へと移行する必要があります。
月次総平均から移動平均への転換
経理部門が月初に多くの時間を費やしている処理のひとつに、原価関連業務があります。製造間接費の配賦や原価差異の算出、棚卸差異の反映など、いわゆる“原価締め”に要する作業量は膨大であり、決算日数短縮を阻むボトルネックのひとつとなっています。
このボトルネックを解消する鍵は、原価計算の仕組みそのものをリアルタイム化することにあります。従来のバッチ処理では、月次総平均法(定期記録法)により、月末に仕入や棚卸、製造間接費などをまとめて平均単価を算出していました。この方法は、月末時点で確定する費用(たとえば棚卸差異や間接費配賦など)を一括で反映できるという利点を持ちながらも、数値が常に“過去”でしか見えないという致命的な欠点を抱えています。
これを、ERP導入を機に継続記録法に基づく移動平均法へ切り替え、在庫評価と原価差異を取引単位で同期させます。
入出庫がリアルタイムに反映されることで、経理は月末を待たずに原価を把握できるようになります。ただし、ユーティリティ費用(電力・ガス・水道など)や給与、外注費、臨時修繕費といった製造間接費の一部は、請求や支給が月末でしか確定しないため、見込み率や仮配賦を用いて日次更新に組み込みます。
標準原価が果たす役割
移動平均法を採用すると、在庫単価や原価差異は取引のたびに更新され、情報の鮮度は格段に向上します。一方で、毎回の変動をそのまま評価指標として扱うと、現場の管理や経営判断がかえって不安定になる場合もあります。ここで軸を与えるのが標準原価です。
標準原価は、工程分析や作業時間、材料消費量などの実績データを基に設定された科学的根拠に基づく合理的な基準コストであり、移動平均で変動する実際原価との差異を通じて、操業効率や配賦精度を評価するための基準として機能します。
リアルタイムに更新される速報値の段階では、主に直接費や変動費(材料費・工賃・外注費など)が中心となり、即時的な改善アクションの対象となります。一方、月末に確定する間接費、例えばユーティリティ費用や臨時修繕費、共通費などは、確定処理を経た上で全体の配賦率や実績原価を補正する管理対象となります。
ミス確認から解放される経理構造へ
移動平均法と標準原価によって、原価領域のリアルタイム化は実現の目途が立ちました。これにより、月初に集中していた原価締めは日次処理へと移行し、経理の負荷は大きく軽減されます。しかし依然として、月末月初には経費や前払費用、管理会計上の部門振替、そして社外請求や支払といった、対外的な確定情報を前提とする処理が残ります。
経理BPRの焦点は、こうした「確定を待つ構造」をどう日次化し、リアルタイムな意思決定の流れに組み込むかにあります。例えば、経費精算をExcelでまとめて月末に登録するのではなく、発生源で即日登録・承認できる仕組みへ変えることで、月末の山を平準化できます。
日々の速報値をもとに行動し、月次の確定値で整合を取る、この二層構造こそが現実的なリアルタイム化です。この仕組みを運用する上で重要なのは、経理が「ミスを探す」立場から「ミスを起こさない仕組みを設計する」立場へと視点を切り替えることです。
リアルタイム化の幻想
ここで注意すべき問題があります。
モノの流れに沿って情報がリアルタイム化すると、おカネの流れも同じ方向に進むはずです。ところが、ERPプロジェクトの現場では、目的に「リアルタイム化」を掲げながらも、実際の設計や構築段階ではその理想が棚上げされるケースが少なくありません。
ヒアリングの段階から新システムがリアルタイムを前提とせずに設計され、最終的にはAs-Isのバッチ処理を引き継いでしまう。しかも、リアルタイムを標榜するベンダーまでもが、その構造的矛盾に気づかないまま従来の処理方式を踏襲してしまうのです。
こうしたズレが積み重なることで、リアルタイム化の意義そのものが形骸化し、結果的に業務サイクル全体が“月次前提”のまま固定化されてしまうのです。
“さしすせそ”が導くTo-Be要求
リアルタイム化が理念だけで終わってしまう現実を防ぐには、進め方そのものに再現性を持たせる必要があります。ここで活きるのが、BPRの調味料“さしすせそ”の視点です。
決算日数短縮というテーマを、“さしすせそ”の視点からTo-Be要求として整理してみます。前回の「在庫削減=モノの流れ」で整えられたリアルタイム化の基盤を前提に、今度は経理領域のBPRをどのように展開できるかを具体的に示していきます。
さ:削減 — 決算日数を短縮するための仕組みを実現すること
- 対象業務:月次・四半期・年次の決算関連業務。
- 業務要求:
- 集計・照合作業を日次処理へ移行し、締めのための特別作業を排除する。
- 現行のバッチ処理前提を見直し、リアルタイムな取引・在庫・会計連動を前提とした構造に再設計する。
- 受入基準:決算処理の短期化と、リアルタイムな経営数値の把握が可能となっていること。
- 優先度:Must
し:視認 — 進捗や異常をリアルタイムに把握できる仕組みを整えること
- 対象業務:伝票承認、原価配賦、在庫・請求管理など決算前工程。
- 業務要求:
- 未承認伝票・原価未配賦・在庫差異などをリアルタイムで検知し、影響範囲を可視化する。
- 社外取引先と入荷・検収・請求情報を連携し、締め後修正や請求遅延を抑止する。
- 水道光熱費・運送費など確定遅延項目は、見なし計上との差異を閾値で管理し、日次で通知・判断できる仕組みを整える。
- 受入基準:異常検知と是正が即時化されていること。
- 優先度:Should(社外)/Could(社内)
す:スピード — 月次仕訳や配賦計算のサイクルを短縮すること
- 対象業務:仕訳計上、配賦計算、残高照合。
- 業務要求:
- 月次仕訳・配賦・残高照合を、締め後の一括処理から日次・随時確定型のプロセスへ転換する。
- 各処理を日常業務フローに組み込み、決算準備を常時進行状態に保つ。
- 受入基準:月初集中作業が解消され、業務負荷が平準化していること。
- 優先度:Should/Could
せ:整理 — 会計データの発生源を明確化し、判断基準を統一すること
- 対象業務:会計仕訳・評価基準設定・勘定科目運用。
- 業務要求:
- 勘定使用ルール、評価基準、計上根拠を全社で統一し明文化する。
- 属人的な修正をなくし、誰が処理しても同一の判断が可能となる標準ルールを整備する。
- 受入基準:会計処理が透明で再現性があり、判断のばらつきが排除されていること。
- 優先度:Could
そ:即応 — 決算締め日数をさらに短縮し、改善を継続する体制を整えること
- 対象業務:部門別締めおよび決算進捗管理。
- 業務要求:
- 部門別締めのリードタイムを定常的に測定し、滞留工程を特定・改善する。
- リアルタイム化・標準化後も、短縮効果を維持・発展させるPDCA体制を構築する。
- 受入基準:決算業務の短縮効果が持続し、即応的な改善が行える体制が確立していること。
- 優先度:Could
まとめ
決算日数短縮の狙いは、業務を急がせることではなく、モノやおカネの流れに合わせて会計処理を連動させることにあります。“さしすせそ”の視点でTo-Be要求を整理することで、決算を「止める行為」から「動きながら整える構造」へと変えることができます。
削減が方向を示し、視認が状況を明らかにし、スピードがリズムを整え、整理が判断を標準化し、即応が改善の持続力を生み出す。この流れが定着すると、決算は単なる経理の締め作業ではなく、企業全体の情報リズムを整える活動へと昇華します。
次回は、Excelで個別に管理され、期末に急増するリベート算出データをリアルタイム化し、決算日数を大幅に短縮したBPR事例を紹介します。データドリブンな経営判断によって、商品点数と在庫を大胆に削減し、利益構造を転換させた取り組みです。企業が“データを起点に意思決定する仕組み”をいかに実現したのかを見ていきます。