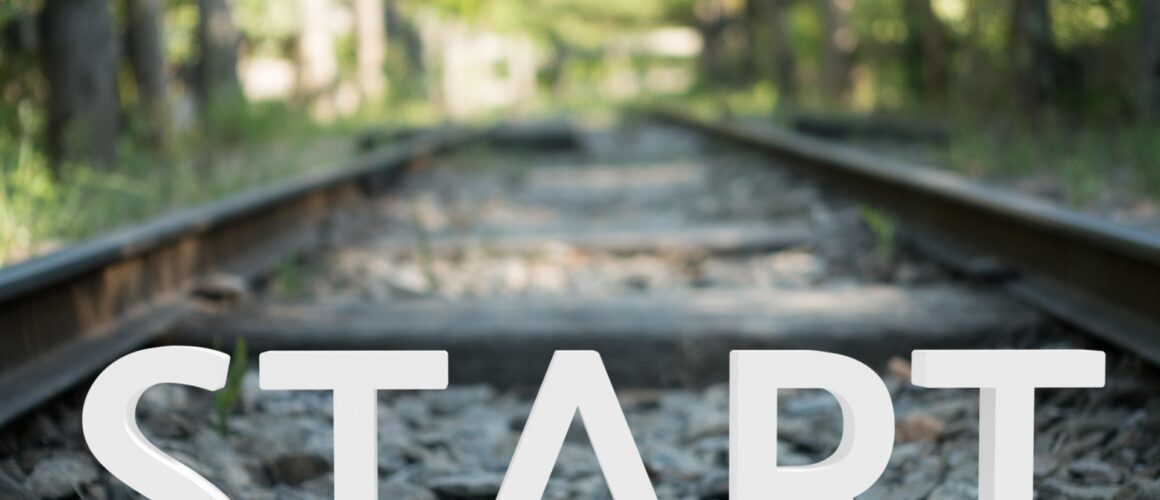SaaSタイプのERPにおける本稼働判定 【実践編】
前回の基礎編では、本稼働判定を構造的に捉えるための4つの評価軸(網羅性/稼働性/適合性/継続性)と、6つの評価領域(ビジネスプロセス/ビジネスデータ/技術/人材/移行/運用)を解説しました。これにより、本稼働の是非を感覚や印象ではなく、体系的に判断するための全体像を整理することができました。
今回の実践編では、評価の考え方を現場レベルの運用へどう具体化するかに焦点を当てます。つまり、評価軸と評価領域の枠組みを踏まえた上で、「何を」「どのように」測定し、「どう報告するか」といった実務レベルでの展開を扱います。
評価の仕組み:再現可能な構造としての本稼働判定
本稼働判定を実務で活用するには、プロジェクトとして何をもって“準備完了”とみなすかという評価基準をまず明確に定めた上で、それを評価軸に沿って、評価領域ごとに評価項目・指標・水準・評点といった判断要素へと具体化する必要があります。
この仕組みは属人的な感覚を排し、ERPや業種を問わずあらゆるプロジェクトで再現可能な構造として設計されます。
具体的には、以下の5つの問いを軸に、評価の仕組みを構築します:
- 何を評価するのか(評価項目):
各評価領域の評価対象を評価できるレベルに細分化します。 - どのように測るのか(評価指標・計算式):
定量指標や算出方法を設定し、評価の一貫性と客観性を確保します。 - いつまでにどれくらいの水準にするのか(評価水準):
フェーズやCRPサイクルといった主要タスクごとに、いつまでにどのレベルを達成すべきかを定めます。 - どのようにスコア化するのか(評点) :
評価指標の結果を点数や信号色などの形式に変換することで、各評価領域の状況を即座に把握できるようにし、関係者間で共通の認識を持てるようにします。 - なぜそのスコアになったのか/ではどうすれば良いのか(評論) :
単なる点数だけでなく、その背景や前提、現場実態、制約条件などを言語化し、「何をどうすれば次に進めるのか」という行動指針を導きます。
ビジネスプロセス領域を例にした構造的な評価の進め方
ビジネスプロセス領域の評価では、業務全体の構造・柔軟性・拡張性を踏まえた多面的な判断が求められます。そのためには、「評価項目→評価指標→評点→評論」という一連の評価ステップを、構造的かつ再現性のある形で設計することが重要です。
評価項目の設定と基本構造
まず、ビジネスプロセス領域における代表的な評価項目は以下の4つです。
- To-Beビジネスプロセスの定義状況
- 他システム連携状況
- 拡張機能開発要件の移送状況
- 将来的な変更に対するプロセスの柔軟性
各評価項目の評価方法とステップ
以下に、各評価項目ごとの評価方法とステップを示します。
1. To-Beビジネスプロセスの定義状況
この評価項目は、本領域における基礎となる評価対象です。評価にあたっては、まず「ものの流れ」を捉える取引パターンと、「情報の発生源」であるトリガーイベントを網羅したTo-Beビジネスプロセスフローを選定することが前提となります。
さらに、その業務フローに対して、事前に整理されたMoSCoW(Must/Should/Could/Won’t)で分類された業務要求をマッピングし、全体としてどの要求がどのフローにマッピングされているかを可視化します。そして、それらがすでに実機上で検証(稼働検証)済みであることをもって、定義の妥当性を評価します。
この評価項目における主な評価指標は次の2点です。
To-Beフローへのマッピング率(網羅性):取引パターン・トリガーイベントを含むプロセスに対して、MoSCoW要求がどの程度マッピングされているかを示す。
稼働率(稼働性):定義されたフローが、実際にCRP等の検証を通じて、想定通りに稼働しているかを示す。
ここで重要なのは、Must要求はすべて実現されていなければならないという前提です。Should要求については、未実現である場合でも、そのリスクに対する代替策(回避手段や後工程の補填)が明確に設計されている必要があります。これにより、To-Beプロセス定義の信頼性と実行性が評価されます。
2. 他システム連携状況
ERP単体ではなく、WMS(倉庫管理システム)やMES(製造実行システム)など他システムとの連携を含めて評価することも、本稼働判定における重要な観点です。業務プロセスの一部が外部システムに依存している場合、それらが定義されたTo-Beフローの中でどのように連携され、実機上で稼働検証されているかを確認します。
この評価項目では、連携I/F成功率を測定し、システム全体としての一貫性と実行可能性を評価します。
3. 拡張機能開発要件の移送状況
この評価項目では、起票された拡張機能開発要件のうち、何件がテストを経て本番環境に移送されたかを評価します。さらに、それらの開発がどのTo-Be業務プロセスに組み込まれているかを明示することで、システムの「標準機能活用度(=適合性)」を定量的に測ることが可能になります。
主な評価指標は以下の通りです:
開発移送率:開発件数のうち、移送完了済件数の割合
開発含有フロー比率:アドオン機能を含むフロー数 ÷ 全フロー数
この情報から、ERPがどの程度標準機能で稼働しており、どこに拡張が必要だったかを明示的に把握することができます。
4. 将来的な変更に対するプロセスの柔軟性
この評価項目は、事業環境や制度改定・組織変更といった将来的な変化に対して、業務プロセスがどれだけ継続的に適応可能な構造になっているかを確認するものです。ここでは「継続性」の観点で、以下4点の評価を行います。
プロセスと設定の文書化:将来的に業務内容や制度が変わった際に備え、どの変更がどのビジネスプロセスに影響し、その際にどのパラメータを変更すれば対応できるのかを、あらかじめ明確にしておきます。
将来対応予定の業務要求の明示とトレース性の確保:MoSCoWにおけるWon’t要求のうち、将来的に重要性を増すものについては「将来対応リスト」として整理され、該当プロセスへの影響範囲がトレースできる状態で管理されていることが求められます。
未利用のERP標準フローおよび機能の整理:現時点で活用していない標準機能が、将来的に業務変化に応じて利用できるよう、どのプロセスに組み込まれうるかを明示・棚卸しておきます。
ベンダーの機能拡張ロードマップの確認と継承設計:ERPベンダーから提供される新機能や拡張モジュールに対して、定期的にロードマップを確認する手順が設けられ、それらの新機能がどのビジネスプロセスにどう適用されるかを業務側で見通し、設計上の備えがなされていること。さらに、将来対応すべき機能に関する知見や判断ポイントが、運用設計書や影響分析メモとして継承・管理されていることも評価されます。
このように、プロセスの再利用性・拡張性・将来対応性を、ビジネスプロセスの構造面から事前に準備・記録・管理していることが、柔軟性・継続性の高さを示す要素となります。
評論の位置づけと役割
各評価項目の結果は、数値や達成率といったスコアに加えて、その背景や判断理由を文章で示す「評論」として報告書に記載します。スコアが同じであっても、前提条件や制約、実行に向けた準備状況が異なれば評価の意味合いは変わるため、数値と評論をセットで扱うことが重要です。
例えば、「To-Beビジネスプロセスの定義状況」に対しては、次のように記述します。
「取引パターンおよびトリガーイベントについては、主要な業務領域での網羅が完了しており、Must要求もフロー上にマッピングされています。ただし、一部の例外処理や新たに発見されたトリガーイベントに関しては、現在対応方針を整理中です。これらは今後の受入テストまでに追加入力・検証が予定されており、現時点では本稼働判定に大きな影響はないと判断しています。全体として、To-Beフローの構造と稼働性には一貫性があり、実装完了率・検証完了率ともに高水準です。」
このように、定量評価の結果と、それに対する解釈や補足を言語化することで、関係者間の認識を揃え、次に進むための判断材料として活用できます。
補足:変化を前提としたアジャイルアプローチにおける本稼働判定の考え方
本稼働判定における評価は、アジャイルアプローチに基づいて進めるべきものであり、評価における「分母(=対象となる業務やフロー)」は、プロジェクトの進行に応じて変化することを前提とする必要があります。
例えば、構想策定フェーズで一通りの業務プロセスが洗い出されていたとしても、業務構築フェーズで実機検証を進める中で、現場の理解が深まり、新たな業務フローや条件が後から見えてくることもあります。こうした変化を「網羅性の不足」と捉えるのではなく、むしろ業務理解の成熟による前向きな進化として評価することが大切です。
また、業界特化型のSaaS ERPを導入している場合であれば、初期段階で見落としていた業務があったとしても、ほとんどの場合、あらかじめ備わっているビジネスプロセスや機能によって補完されます。そのようなプロセスを実機検証を通じて追加で分母に加え、継続的に評価の網羅性と稼働性を高めていくと言った柔軟な対応ができるのです。
このように、本稼働判定の評価においては、あくまで「現時点での把握状況」を出発点としつつも、それを固定化せず、プロジェクトの成熟度に応じて評価対象を見直していく柔軟性こそが、SaaS ERPにおけるアジャイルな評価設計の本質であるといえます。
まとめ
本稼働判定は「できそうか」の感覚論ではなく、「何をもって準備完了とみなすか」をあらかじめ定義し、その上で構造的に判断していく仕組みです。基礎編で提示した評価軸と評価領域の全体像を土台に、実践編ではその中身をどこまで定義し、どう測り、どう報告し、どう次の行動につなげるかを具体的に示しました。こうした再現可能な構造によって、プロジェクトの属人性を減らし、組織として納得感をもって本稼働の可否を判断することが可能になります。SaaS ERPという変化し続ける環境においてこそ、このような評価設計の視点が経営の意思決定を支える重要な基盤となります。
なお、今回の実践編では、6つの評価領域のうち「ビジネスプロセス領域」に焦点を当て、評価項目とその評価方法を構造的に示しました。他領域の、ビジネスデータ、技術、人材、移行、運用、についても、同様の考え方に基づいて評価のフレームワークを設計しており、今後それらも順次共有していく予定です。本稼働判定の全体像を実務で活用するための参考として、引き続きご活用いただければ幸いです。